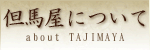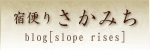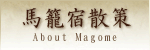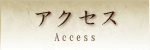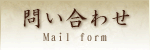馬籠宿散策


馬籠宿散策
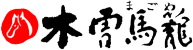
中山道六十九次のうち木曽路には十一の宿場がおかれていました。
馬籠宿は板橋から数えて四十三番目となります。江戸(東京)からの距離は約八十三里(約333km)となります。宿場は山の尾根に沿った急斜面にあり、通りに面した建物は石垣をくんで建てられています。周りの自然・山々の四季の変化もお勧めです。坂の町・馬籠宿の石畳を歩いてみて下さい。
| 藤村記念館 | |
|---|---|
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
昭和22年2月17日の藤村誕生日に馬籠の壮青年を中心とした同志の人々が菊地重三郎氏を核にふるさと友の会を結成。同年11月15日この人たちにより落成式。数多くの資料が収蔵されています。馬籠宿の真中に位置しシンボル的存在です。馬籠に来たら必ず見てください。
【開館時間】 ・4月〜11月 午前9:00〜午後5:00 (入館は午後4:45まで) ・12月〜3月 午前9:00〜午後4:00 (入館は午後3:45まで) 【休館日】 *12月〜2月の毎週水曜日 入館料 大人550円 小中学生100円 |
|
| 清水屋資料館 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
初代から馬籠の組頭、そのほか要職をつとめた家で島崎家と深い関係に
あった原家。藤村の作品”嵐”の中に当家8代「原 一平氏」が 「森さん」役ででています。藤村の書簡や、父正樹・富岡鉄斉らの 掛け軸等が数多く収蔵されている。 【入館料】おとな150円 こども100円 【問い合せ】0573-69-2108 |
|
| 馬籠脇本陣資料館 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
八幡屋所蔵の記録、版本、什器類、類山村家よりの拝領品や宿関係の史領や器具類、民具類などが陳列されている。大名が利用した上段の間が忠実に復元されています。
【入館料】おとな150円 こども100円 【問い合せ】0573-69-2558 |
|
| 永昌寺 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
永禄元年(1558年)の建立と言われ、その後いくたびか建て替えられ現在
にいたっています。藤村の「夜明け前」では「万福寺」として登場します。 藤村の墓地もここにあります。 本堂横のお堂には円空作の聖観音像が安置されています。 【耳より情報】 毎年12月31日の大晦日から元旦にかけて鐘撞き堂で「除夜の鐘撞き」が行われます。来た人どなたでも撞く事ができます。何とも言えない心にしみいる音色が響きます。(無料) |
|
| 馬籠の展望台 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
ある個人の方のご好意より馬籠宿の一番上に立派な展望台ができまし
た。近くの山々や宿場が一望できます。ここから見える恵那山は最高 の眺めです。妻籠へ歩かれる時もここを通りますので、是非一度訪れ てみて下さい。 |
|
| 枡形と水車・常夜燈 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
馬籠宿下入り口より100mほどの車屋坂と言う所に大きな水車小屋があります。ここに馬籠宿の枡形があります。江戸時代、各宿場の入り口には「枡形」と呼ばれる空間が設けられていました。
馬籠の枡形は急斜地に設けられたため石段の造りとなっています。 2010年よりマイクロ水力発電がこの水車を使い行われています。 小さな小さな水力発電ですが、将来的にもソーラーに次ぐ様なエコ発電に なればと思います。 【耳より情報】 枡形をゆっくり歩いたほうが急な坂道を歩くより楽に歩けます。 |
|
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
宿場町の夜道を水車の発電により灯りで照らします。
昔は街道の道しるべとしてありました。 |
|
| 五輪様 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
その昔、木曽義仲の異母妹菊姫の墓と伝えられている。
【場所】 永昌寺より(徒歩5分)県道を渡った所 |
|
| 十曲峠(じゅっきょくとうげ)・石畳・是より北木曽路 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
【落合の石畳】美濃路は落合宿から馬籠宿にさしかかると、深い立ち木の中に石畳が昔のままに残っています。石畳は一種の舗装道路で、急な坂道の路面流失を防ぐ為に設けられたものと言われます。石畳の坂を登りつめるあたりを十曲峠(じゅっきょくとうげ)と言い木曽路と美濃路の境になります。
【場所】 馬籠から徒歩約25分 車で5分 |
|
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
【是より北木曽路】の碑この碑は新茶屋付近(美濃路と木曽路の境)にあります。島崎藤村先生が地元の人達の要請に応えて書いたものです。碑が建てられたのは藤村没後の昭和32年で「ふるさと友の会」の10周年記念事業によるものだそうです。
|
|
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
【松尾芭蕉】の句碑「送られつ 送りつ 果は 木曽の穐」場所は是より北木曽路の碑の近く(新茶屋)句碑が建てられたのは天保13年(1842)で、芭蕉の没後158年にあたります。当時、この地方には芭蕉を祖師とする俳人が多く、この門人たちによってたてられたそうです。藤村の小説「夜明け前」には、この除幕の当日のことが書かれています。
|
|
| サンセットポイント | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
十曲峠途中にあるあずまや付近から美濃路(中津川市街方面)を見ると中々の眺めです。夕日も綺麗です。(旧/信州サンセット100選)
【正岡子規】の句碑「桑の実の 木曽路出づれば 穂麦かな」子規 正岡子規(1867-1902)は明治期の俳人・歌人。本名は常規、松山の出身。明治26年東京大学を中退後俳句革新を唱え、さらに「歌よみに与ふる書」で万葉を理想とする短歌革新を唱えた。 「かけはしの記」には、この句の前に「馬籠下れば山間の田野照稍々開きて麦の穂已に黄なり。岐蘇の峡中は寸地の隙あらばここに桑を植え一軒の家あらば必ず蚕を飼うを常とせしかば、今ここに至りて世界を別にするの感あり。」と述べている。この碑は昭和54年9月、馬籠観光協会によって建立されました。 |
|
| 馬籠宿街道ギャラリー | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
馬籠宿の街道を使ったギャラリーを年数回行います。
20回を超えましたが野の花を使った花の展示が多いです。 どなたか作品を展示してみたい方は 馬籠観光協会0573-69-2336までお問い合わせ下さい。 |
|
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
|
|
| 東山魁夷/心の旅路館 | |
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
|
|
| タクシーで行くいいとこめぐり | |
|
木曽路と美濃路をご案内しいます。
|
|
| 馬籠宿 イベントカレンダー | |